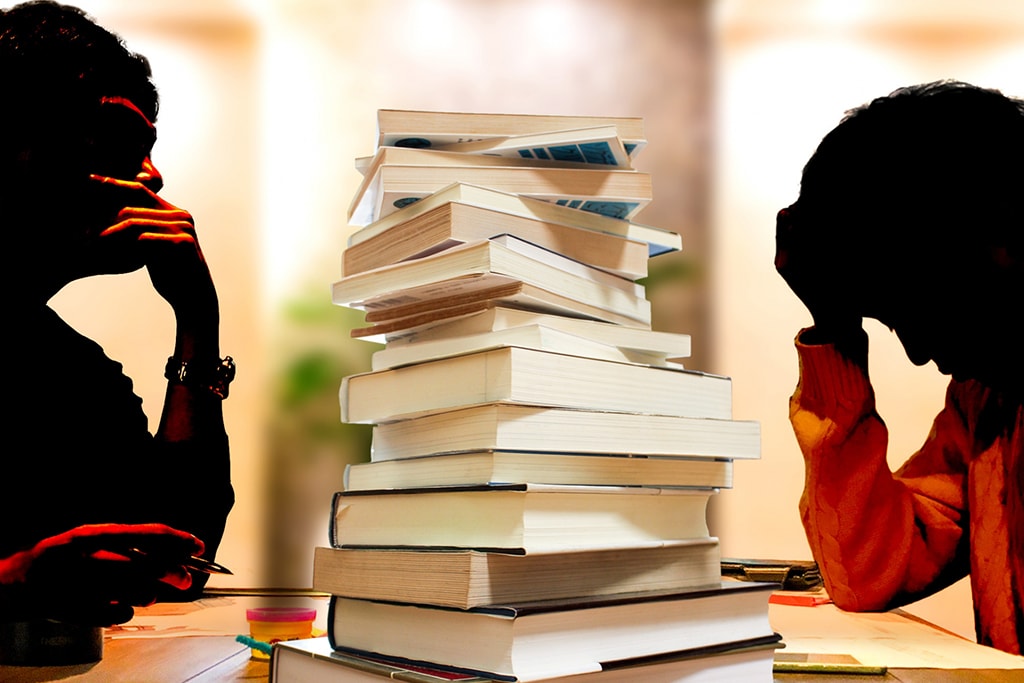建設業経理士の1級の検定試験には、財務諸表、財務分析、原価計算の3科目の受験と合格が必要で、それぞれに適した勉強方法を自分なりに工夫する必要があります。
財務諸表と原価計算のふたつの科目は、建設業経理士の2級までの検定試験の出題内容を発展させた問題が出題されますので、基礎をしっかりと作っておくことが前提条件となります。
財務分析は、建設業経理士1級で初めて出てくる内容がほとんどで、簿記の知識に加えて企業の経営状況を判断するための技量が求められ、たくさんの公式を覚えて計算する必要があります。
建設業経理士1級の検定試験の勉強方法には、2級までの学習内容を踏まえたうえで、各科目の特徴を見極めた勉強方法を組み立てます。
建設業経理士の原価計算の勉強方法
建設業経理士1級の検定試験の科目の中で、これまでの平均合格率が3科目の中で最も高いのが、原価計算ですが、最近の傾向は多少変化がみられる科目でもあります。
原価計算は、会計基準や建設業に関連する法令の影響を最も受けにくく、理論よりも計算の比重が大きい特徴があります。
建設業経理士2級で出題される計算問題や完成工事原価報告書の作成問題の知識を発展させた内容と考えられ、日商簿記の工業簿記などとの共通点も多い内容です。
出題内容もパターン化されるものが多く、その組み合わせによって、解法に混乱をきたすことも予想されます。
原価計算の勉強方法では、過去問題から自分なりの解法をパターン化したモデルをつくりあげておくことが重要です。
そのパターンをしっかりと身につけることで、本番の検定試験で戸惑うことなく計算処理が行えます。
建設業経理士の原価計算のパターンをつかむための勉強方法
建設業経理士1級の検定試験の財務諸表や財務分析では、理論が求められる比率が一定割合で存在しますが、原価計算は理論問題の比率が低く、計算問題の配点が多い傾向にあります。
原価計算の計算問題もパターン化された問題が多く、基本となる解法の計算式を記憶し、過去問題集の反復練習を繰り返してパターンを習得することが勉強方法です。
過去問題集を反復することで、解法の基本的なパターンを自分なりにノートなどに書き出して作ることも勉強方法といえます。
計算問題のパターンを記憶することと、過去問題の反復、問題集の類似問題での演習を繰り返し、積み上げていくことが大切です。
建設業経理士の原価計算の攻略には過去問題の反復練習
建設業経理士1級の検定試験にある原価計算の科目は、他の科目と違いパターン化された計算問題が出題される傾向があります。
そのため、原価計算に関しては、2級までに出題される計算問題の解法の理解と1級で出題された過去問題を反復練習する中で、解法パターンを記憶することが攻略するための勉強方法です。
原価計算以外の科目では、理論と計算の両方に対策が必要ですが、原価計算に関しては、計算問題に対する勉強方法を自分なりに工夫することが合格のコツになります。